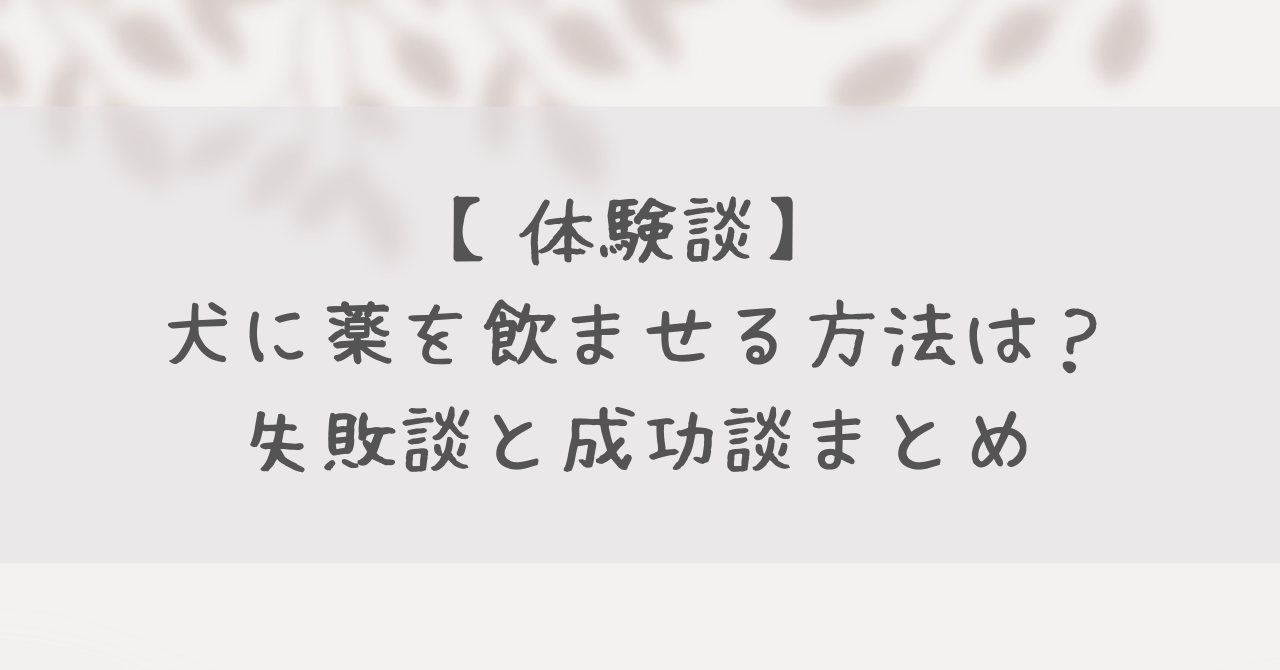考えたくはないことですが、大切な家族である愛犬が亡くなったとき、悲しみの中でもやらなければならないことがいくつかあります。
私自身、愛犬が虹の橋を渡ったとき、どうしていいか分からず戸惑ったことがありました。
この記事では、私の体験を交えながら、「犬が亡くなったらやること」を順を追ってご紹介したいと思います。
📝 愛犬が亡くなったらやること(流れまとめ)
最初に、愛犬がなくなったらやることの流れをまとめました。

- 体を清めて安置する(保冷剤などで一時的に保存)
- 火葬・葬儀の方法を決めて手配する
- 役所への死亡届を提出する(必要な場合)
- 遺骨や思い出の品を整理・保存する
- 心のケアを大切にする(ペットロスの対処)
これらの愛犬が亡くなったらやることをこのあと1つずつ、私の体験談も交えてながら、詳しく見ていきたいと思います。
📝 愛犬が亡くなったらやること
愛犬が亡くなったときは、病気や老衰で少しは心構えができていたとしても、突然だったとしても悲しいことにかわりはありません。
まずは、思いっきり悲しんでいいと思います。
私の場合、愛犬は闘病中でしたが諦めてはいなかったので、本当に悲しくてひとしきり泣きました。
その後、少し落ち着いてから(といっても泣きながら頭は混乱状態ですが)やらなければいけないことがあると思い調べ始めました。

1.体を清めて安置する
少し落ち着いたら、まずは愛犬の体を清めて安らかに眠れる状態 にしてあげましょう。
亡くなった直後は、体の組織が働かなくなる影響で、遺体の口やお尻から体液が出ます。
愛犬の体にも体液が付いているので、できる範囲で綺麗にしてあげるのが良いと思います。
また、犬や猫は亡くなってから2時間ほどで死後硬直が始まるため、棺に納まるように手足を曲げてあげることをおすすめします。
愛犬はしばらくシャンプーも出来ていなくてボサボサだったので、綺麗にしてあげたいと思いました。
最初、かかりつけの病院に連絡しようと思いましたが診療時間外だったので、お世話になっていたトリミングサロンに連絡してみました。
こころよくエンゼルケアを引き受けて下さったのですぐに愛犬を連れて行きました。
当日のトリミングは全て終わった後で、営業時間外に対応して下さいました。
病院やトリミングサロンに行かなくても、家族みんなで自宅で綺麗にしてあげるのもとても良いと思います。
その後は、葬儀までの間、ドライアイスや保冷剤で愛犬の遺体を保冷します。
2. 火葬・葬儀の手配をする
次に、愛犬の遺体をどうするかを決める必要があります。
多くの場合は「ペット火葬」になりますが、いくつかの選択肢があります。
- 動物霊園・ペット火葬業者に依頼
- 自治体の火葬サービスを利用(市町村によって異なります)
- 自宅での埋葬(※禁止されている地域もあります)
1の場合でも、最近は移動式のペット火葬もあるので、自宅で火葬をされる方もいらっしゃると思います。
私の愛犬は動物霊園で火葬と葬儀をしていただきました。
お花や祭壇もきちんとしていただけて、他人の目も気にせずゆっくり見送ることが出来たので、動物霊園で良かったと思っています。
遺骨は自宅供養するため、家に持ち帰らせていただきました。
3. 役所への届出(必要であれば)
犬は「畜犬登録」されているため、亡くなったら自治体に死亡届を出す必要があります。
自治体によって手続き方法は異なりますが、主に以下の内容を伝えます。
- 飼い主の情報(住所・氏名)
- 犬の登録番号
- 犬の死亡日
正直、届け出を出さないといけないのかもよくわかりませんでしたが、わざわざ市役所に行く気にもなれなかったので、郵送で手続きをしました。
4. 愛用品の整理とメモリアルの準備
少しずつ気持ちが落ち着いてきたら、愛犬の首輪やリード、おもちゃや服などの整理をします。
愛犬との思い出を大切にしたい方は、メモリアルグッズを作るのもおすすめです。
家に飾ることが出来たり、身につけたり出来るメモリアルグッズには次のようなものがあります。
- 遺骨ペンダント
- 遺骨キーホルダー
- 写真入りフォトフレーム
- 思い出アルバム
最近は他にも様々な愛犬グッズを作る事ができるので、自分にあった愛犬のメモリアルグッズが見つかると思います。
愛犬が亡くなってから作ったメモリアルグッズとしては、火葬の前にとった手形足形と遺毛入りペンダント、遺骨キーホルダー、遺毛入り羊毛フェルトなどがあります。
愛犬グッズの種類が豊富なので、まだまだ作りたい愛犬グッズがたくさんあります。
ですが、費用もかかるので少しずつ作って増やしていくのも楽しみの1つになっています。
5. 心のケア
ペットロスは、想像以上に心に影響を与えるものだと思います。
誰かに話したり、泣いたり、思い出を語ったりすることで心の回復につながることもあるので、必要であればカウンセリングやSNSコミュニティに頼るのも大切です。
私は愛犬の遺品や写真を整理しながら、少しずつ心の整理をしました。
今でも写真や動画を見て涙が出ることもありますが、SNSで同じ様な経験をした人の投稿を見たりして、私も頑張らないとと思っています。
おわりに
愛犬が亡くなることは、本当に辛い経験です。
でも、きっと愛犬は幸せだったはずと思って、私も前を向いて頑張ることにしました。
私の経験が少しでもお役に立てたら幸いです。